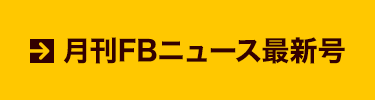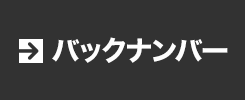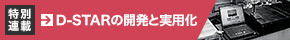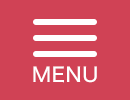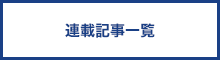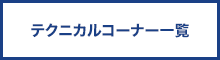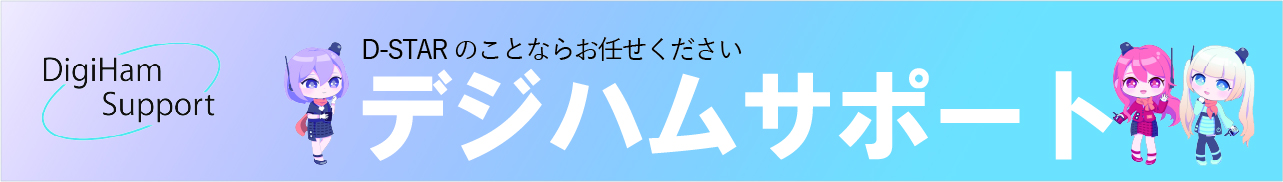アパマンハムのムセンと車
第35回 モービル&アパマン運用に役立つヒント
2025年8月15日掲載
連載35回目となります。先日のフィールドデーコンテストはいかがでしたでしょうか? 私は仕事が多忙であったこともあるのですが、ついうっかり見過ごしてしまいましたhi こんなんじゃいけないですね~ 次は全市全郡コンテストに参加予定です。皆さんとお会いできるのを楽しみにしています。
コンテストはともかく、これからお盆の時期、今では夏休みの時期とでもいいましょうか、通常の月よりも休みが多くなります。業界によっては夏休みがない(交代で取る)ところもあるかも知れません。
私が関わっている車業界は、いちばん大元の自動車メーカーが休みを取ります。そのため、業界全体が休みになってしまいます。普段の休みが少ないこともあって、この時期(他にGWと年末年始)にまとめて休むのが慣例になっています。まとめて休みが取れるのはとってもいいことです。移動運用するにも、普段行けないようなところに遠征できますから。
さて、お盆とは、夏季に祖先の霊を祀るための日本の伝統的な行事です。仏教の「盂蘭盆会(うらぼんえ)」と、古来の祖霊信仰が結びついて現在の形になりました。お盆の期間中、祖先の霊が一時的に家に帰ってくると考えられており、家族で霊を迎え、供養する大切な期間とされています。
お盆の期間は地域によって異なりますが、大きく分けて3つのパターンがあります。
・月遅れ盆(8月盆)
期間: 8月13日~16日
特徴: 全国の多くの地域でこの期間にお盆が行われます。
・新盆(7月盆)
期間: 7月13日~16日
特徴: 東京、横浜、静岡など、一部の都市部でみられます。明治時代の新暦採用に伴い、時期が変更されたため「新盆」と呼ばれます。
・旧盆
期間: 旧暦(太陰暦)の7月15日を中心とした期間
特徴: 沖縄地方などで、現在も旧暦に基づいてお盆が行われています。そのため、毎年日程が変わります。
お盆の伝統的な過ごし方には、以下のようなものがあります。
・迎え火、送り火
迎え火: 13日に、祖先の霊が道に迷わないように焚く火。
送り火: 16日に、祖先の霊を送り出すために焚く火。
・お墓参り
お盆の期間中に家族揃ってお墓参りに行き、ご先祖様を供養します。
・精霊棚(盆棚)の飾り付け
ご先祖様の位牌や供物を飾り、ナスやキュウリで作った「精霊馬(しょうりょううま)」を飾ります。

精霊馬
・家族や親戚との集まり
お盆休みを利用して、実家に帰省し、親戚が集まって故人の思い出話などをします。お盆休みは、お盆の時期に合わせて企業などが設ける休暇のことです。国民の祝日とは異なり、法律で定められたものではありませんが、多くの会社が8月13日~16日頃を休暇としています。
お盆休みの過ごし方は、伝統的なお盆の行事だけでなく、個人のライフスタイルに合わせて多様化しています。
帰省: 実家に帰り、家族や親戚と過ごす。
旅行: 国内や海外へ旅行に出かける。
自宅で過ごす: 趣味に没頭したり、家族とゆっくり過ごしたりする。
お盆休みは、ご先祖様を供養する伝統的な意味合いを持ちつつ、現代においては家族や個人の時間を大切にする期間にもなっています。

お盆といえばコレ! 盆踊り
皆さんのお盆の過ごし方はどれでしょうか? 私は例年通り、仕事ですかねぇhi 余談ですが、盆踊りのことを英語で「Bon Dance」というんだそうです。面白いですね。
今回は電気自動車の話です
今回は電気自動車(EV)について、お話していこうと思います。「EV」は「Electric Vehicle」の略で、電気自動車のことです。自宅や充電スタンドなどで車載バッテリーに充電を行い、モーターを動力として走行します。
我が国で初めて量産された電気自動車は三菱自動車の「アイ・ミーヴ」です。その後発売された日産自動車の「リーフ」によって、市場に電気自動車が認知されていきました。

アイ・ミーヴ

リーフ
まず、電気自動車の歴史です。電気自動車は、実はガソリン車よりも古く、大きく3つの時代に分けられます。
第1期: 黎明期(19世紀後半~20世紀初頭)
電気自動車の誕生: 1820年代にハンガリーのイェドリク・アーニョシュが電動機を開発し、模型車両を動かすことに成功したのが始まりとされています。その後、1880年代にはフランスのギュスターヴ・トルヴェが充電可能なバッテリーを搭載した三輪EVを発表し、本格的な電気自動車の歴史が始まりました。
ガソリン車との競争: 自動車の黎明期には、蒸気自動車、ガソリン自動車、電気自動車がしのぎを削っていました。この頃は、電気自動車の方がガソリン車よりも静かで振動が少なく、操作も容易だったため、特に都市部の富裕層や女性に人気がありました。1899年には電気自動車が初めて時速100kmを突破するなど、技術的にも優位に立つ時期がありました。
ガソリン車の台頭: しかし、航続距離の短さや充電時間の長さが課題となりました。そこに、アメリカのヘンリー・フォードが「T型フォード」を大量生産し、安価で長距離を走れるガソリン車を普及させたことで、電気自動車は次第に市場から姿を消していきました。
第2期: 衰退と復興の試み(20世紀中頃~)
ガソリン車優位の時代: 20世紀に入ると、石油の大量採掘と精製技術の発展により、ガソリン価格が下落し、ガソリン車が圧倒的に優位な時代となりました。電気自動車は、ごく一部の特殊用途(工場内の運搬車など)を除いて、ほとんど姿を消しました。
環境問題への関心: しかし、1960年代頃から大気汚染などの環境問題が顕在化し始め、電気自動車への関心が再び高まりました。各国の自動車メーカーや政府は、クリーンなエネルギー源として電気自動車の研究開発を再開します。
日本での開発: 日本でも、第二次世界大戦後のガソリン不足を背景に、電気自動車の開発が盛んに行われた時期がありました。特に1947年に発売された「たま号」は、東京電気自動車(後の日産自動車)によって製造され、日本の電気自動車史において重要な役割を果たしました。
第3期: 再度の普及と現代(21世紀~)
リチウムイオンバッテリーの進化: 2000年代に入ると、リチウムイオンバッテリーの性能が飛躍的に向上し、航続距離や充電時間といった従来の課題が大幅に改善されました。
テスラ社の登場: 2008年にテスラ社が「ロードスター」を発売したことで、電気自動車は単なるエコカーではなく、高性能でスタイリッシュな車として注目を集めるようになります。
世界のEVシフト: 現在、地球温暖化対策や環境規制の強化を背景に、世界各国でEVシフトが加速しています。中国やヨーロッパを中心に、電気自動車の販売台数は急増しており、各国の政府も補助金制度などを通じて普及を後押ししています。
日本での現状: 日本では、ハイブリッド車(HV)が市場の多くを占めていますが、近年は日産「サクラ」や三菱「eKクロスEV」といった軽EVの登場により、徐々に普及が進んでいます。しかし、世界に比べると充電インフラの不足や車両価格の高さが課題として残っています。

充電中の電気自動車
このように、電気自動車の歴史はガソリン車との競争、そして環境問題への関心の高まりによって、浮き沈みを繰り返しながら現在に至っています。
電気自動車に無線機を付けるには
電気自動車(ハイブリッド車も同様ですが)には、2つのバッテリーが搭載されています。ひとつはモーターを回して走行するメインバッテリー、もうひとつは補機類(ヘッドライトやブレーキライトなど)のための補機用バッテリーです。
メインバッテリーは走行用ですので、大きく、高電圧で、容量もあります。補機用バッテリーは、通常のガソリン車のバッテリーくらいの大きさ、容量で、電圧は一般的に12Vとなっています。無線機を接続するときは、こちらの補機用バッテリーにつなぎます。

補助バッテリー(黄色の○印の部分)
接続時に注意する点は、通常のガソリン車と同じです。補機用バッテリーはメインバッテリーによって充電されています。ガソリン車がオルタネーター(発電機)で充電されているのと同じですね。
注意する点は、メインバッテリーから充電されるということはその分走行用のエネルギーを消費しているということです。移動運用に夢中になって、メインバッテリーを消耗させてしまって帰れなくなる、なんてことのないように注意しましょう。移動運用するなら、ポータブル電源や市販のガソリン車用バッテリーなど、別の電源を確保しておくべきでしょう。

電気自動車のバッテリーを再利用したポータブル電源(JVCKENWOOD Webサイトより)
なおご意見、ご感想、ご質問等については、筆者である私宛(jf1kktアットマークgmail.com)へご連絡頂けますと幸いです。
アパマンハムのムセンと車 バックナンバー
- 第40回 モービル&アパマン運用に役立つヒント
- 第39回 モービル&アパマン運用に役立つヒント
- 第38回 モービル&アパマン運用に役立つヒント
- 第37回 モービル&アパマン運用に役立つヒント
- 第36回 モービル&アパマン運用に役立つヒント
- 第35回 モービル&アパマン運用に役立つヒント
- 第34回 モービル&アパマン運用に役立つヒント
- 第33回 モービル&アパマン運用に役立つヒント
- 第32回 モービル&アパマン運用に役立つヒント
- 第31回 モービル&アパマン運用に役立つヒント
- 第30回 モービル&アパマン運用に役立つヒント
- 第29回 モービル&アパマン運用に役立つヒント
- 第28回 モービル&アパマン運用に役立つヒント
- 第27回 モービル&アパマン運用に役立つヒント
- 第26回 モービル&アパマン運用に役立つヒント
- 第25回 モービル&アパマン運用に役立つヒント
- 第24回 モービル&アパマン運用に役立つヒント
- 第23回 モービル&アパマン運用に役立つヒント
- 第22回 モービル&アパマン運用に役立つヒント
- 第21回 モービル&アパマン運用に役立つヒント
- 第20回 モービル&アパマン運用に役立つヒント
- 第19回 モービル&アパマン運用に役立つヒント
- 第18回 モービル&アパマン運用に役立つヒント
- 第17回 モービル&アパマン運用に役立つヒント
- 第16回 モービル&アパマン運用に役立つヒント
- 第15回 モービル&アパマン運用に役立つヒント
- 第14回 モービル&アパマン運用に役立つヒント
- 第13回 モービル&アパマン運用に役立つヒント
- 第12回 モービル&アパマン運用に役立つヒント
- 第11回 モービル&アパマン運用に役立つヒント
- 第10回 モービル&アパマン運用に役立つヒント
- 第9回 モービル&アパマン運用に役立つヒント
- 第8回 モービル&アパマン運用に役立つヒント
- 第7回 モービル&アパマン運用に役立つヒント
- 第6回 モービル&アパマン運用に役立つヒント
- 第5回 モービル&アパマン運用に役立つヒント
- 第4回 モービル&アパマン運用に役立つヒント
- 第3回 モービル&アパマン運用に役立つヒント
- 第2回 乗用車でのマルチバンド運用を考える
- 第1回 モービル運用を考える
外部リンク
アマチュア無線関連機関/団体
各総合通信局/総合通信事務所
アマチュア無線機器メーカー(JAIA会員)